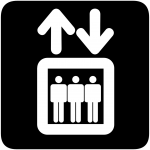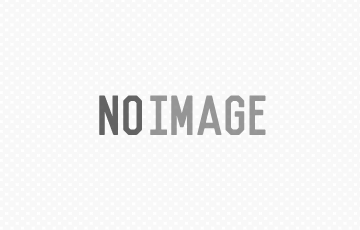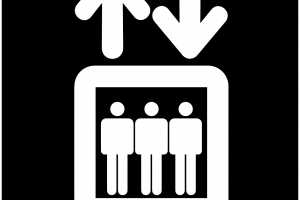- 介護施設で親が亡くなった時、どうしたら良いのだろうか
- 叔父や叔母が施設で入居中、その後の事を考える必要がある
という時にの手順を解説致します
目次
危篤~ご臨終
入居先の施設へ向かいましょう
まず、ご危篤(危うい状況になった時)状態になられた時には施設の方から連絡が入ります
緊急時のため、焦りつつも落ち着いて施設へ向かいましょう
施設に向かう途中で家族や親族に連絡を入れていくと良いでしょう
「万が一の時に連絡先リスト」を作っておくと安心です
ご臨終を迎えたら
医師が死亡診断書を書きます
死亡診断書を受け取ります
死亡診断書の原本は1部で構いません
真夜中の場合、翌朝になってから医師が死亡診断書を発行するときもあります。
(事前にお看取りの際の医師の対応を確認しておくと良いでしょう)
施設職員がエンゼルケア(死後処置)を行ってくれます
(施設によっては何もしないという事も稀にありますので事前に確認をしておきましょう)
その間に葬儀社に連絡を入れます。
連絡したときに伝えること
- 入居先の施設名
- お亡くなりになられた方のお名前・住所
- 連絡を取れる方のお名前・住所
- 安置先(自宅もしくは霊安室の希望を伝えます)
- 何時になったら施設から移動が可能なのか
以上のことを伝えます
お迎え~
お部屋で待機します
お部屋の荷物をまとめておきます
「なかなか写真を撮る機会がなかったので写真を探さないといけない」という状況がよくあります
荷物をまとめる際に、施設の行事等で撮って頂いたお写真を持っておくと良いです
遺影写真を作るときに必要となります。
また、納棺を行う際にお顔を整える時の参考にもなりますので写真は持っておいて損はないです
お迎えが来たら葬儀社のスタッフがストレッチャーにお乗せ換えをします
介護施設の職員の方もお手伝いしてくれることが多いです
寝台車にお乗せしたあと安置先へ向かいます
(出発する前に施設の方へのお礼の挨拶を忘れずに行いましょう)
安置場所
霊安室では面会できるところとできないところがあります
霊安室に安置の場合、状況によっては施設でお見送りをして
その後自宅で打ち合わせを行う場合もあります。
自宅に安置もしくは霊安室に安置をするかは事前に決めておいた方が良いです
打ち合わせ~
葬儀の日程や内容の取り決めを行う打ち合わせを行います。
ここで先ほどの写真が必要となります
写真がないとまた施設に足を運ばないといけない可能性があるためです
施設の方が葬儀に参列されることは、正直施設長の考え方によります
参列できない場合は、弔電や供花をお出しになることがあります
無碍に断らないことをおすすめいたします。
納棺式
お棺にお納めする納棺式を執り行います
とても理解のある施設の場合、納棺式まで施設のお部屋で行っても大丈夫なところもあります
事前に確認ができるのであれば確認しておくと良いかもしれません
入居されていたお部屋で納棺式ができると施設の職員の方々もお別れができるので良いと思います
お通夜~
お通夜
夕方に葬儀を行う場所に集合となります
自宅や寺院、最近は斎場(セレモニーホール)が多いです
自宅に安置されている状態から斎場で葬儀を行う場合、
自宅から故人を見送る『門送り』を行います
近所の方にも門送りしてもらえると良いですね
関東では18時~のお通夜が多いです
葬儀・告別式
午前中に集まり葬儀・告別式となります
厳密に言うとお花入れを行うなどお別れをする場面を告別式と言います
出棺
火葬場へ移動します
荼毘~収骨
火葬場にて荼毘に付されます
時間になると収骨を行います
場所によっては荼毘中に会食を行う斎場もあります
初七日
本来であればお亡くなりになられてから7日目に行う初七日の法要を行います
葬儀に組み込んで行う場合もあります
会食
葬儀に参列された方(主に家族・親族)で会食となります
散会
無事に終了したことの報告とお礼を伝えます。
この時点で49日法要の日時も伝えておくと良いでしょう
お骨のご安置
自宅用の祭壇にお位牌、お骨をご安置しお写真を飾ります
まとめ
以上が介護施設でお亡くなりになられた場合の流れとなります
- 医師が死亡診断書を書いてくれるのか
- 施設ではいつまで安置が可能なのか
- どの写真を遺影写真として使うのか
事前に確認をおすすめいたします
お問い合わせはこちらからお願いします