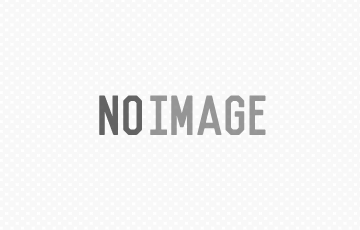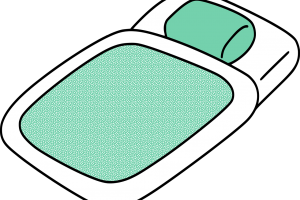『家族葬にしようと思って』『うちうちだけで行う葬儀にしたくて』と葬儀の打ち合わせの際や事前のご相談の際に良く聞くケースです
結論から言うと、呼ぶ範囲に法律的な決まりはありません
しかし、今まで見てきた経験からすると
目安は三親等ぐらいまでとなっています
三親等はどこまでなのか
例えば父親が亡くなり、喪主は長男となった時には
①長男家族(例:4人)
②次男家族(例:4人)
③父親兄弟(伯父伯母)(例:3人)
④母親姉弟(叔父叔母)(例:2人)
⑤孫家族(例:0人)
⑥父方甥姪(例:3人)
⑦母方甥姪(例:2人)
⑧長男の嫁父母(例:1人)
⑨次男の嫁父母(例:2人)
⑩長男の嫁姉弟(例:2人)
⑪次男の嫁姉弟(例:1人)
と目安ですが上げていくと考えやすくなります。(例合計:24人)
特別な事情がなければ三親等を目安に呼ぶとすると10~30人くらいの規模になると想定されます。
逆にこの範囲で行っておくと葬儀後も安心だと思います。
本当の身内だけという方も稀にいらっしゃいます
上記の目安からすると①と②と③だけで行う場合です
4~10人くらいの規模になると思います
その際には
『葬儀は家族だけで行います』と葬儀前に告知しておくのか
『葬儀は家族だけで行いました』と葬儀後に告知するのか
どちらかの形を取ることになります。
ちなみに呼ばないケースを取られる理由としては
『自死や不慮の事故の場合』
『親戚があまりにも遠方にいる場合』となっています
遠方といっても同じ関東圏にいても遠いからという理由にされる方もいらっしゃいます
関西圏だからという方もいらっしゃいます
遠いというよりは日頃から付き合いのない親戚に対してどうして良いか分からない(煩わしい)というのが
本当の理由ではないでしょうか
人が集まれば気を遣う事も出て来ます
ただその気を遣う場面や対応の仕方を経験で知っているのが葬儀屋さんです
そのために葬儀屋さんがいます
人が集まるからこそ悲しみを皆で受け入れることができます
家族葬の親族を呼ぶ範囲から少し話はそれましたが
だからこそ呼べる家族葬にして頂きたいと思います