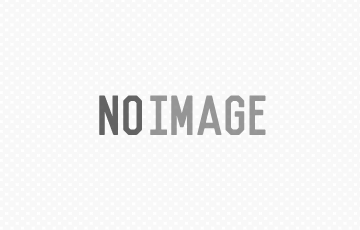現在では葬儀(告別式)に組み込んで先に初七日を行い、葬儀が終わってから火葬場に移動をして火葬を行い、お遺骨を自宅に持ち帰ってからは49日まで家族が自宅にて供養を行う事が一般的となっています。
そもそも49日法要とは?
元々は初七日・二七日・三七日・四七日・五七日・六七日・七七日と七日ごとに法事を行っていました。この世とあの世の間にある世界を”中有”や”中陰”と呼び、その期間が49日間続くと言われています。この49日間に次の世界としてどこに生まれるかが決定されると信じられています。この中陰の期間が済むことを”満中陰”と呼んでいます。この日に死後の世界が決定されますので七七日忌(49日)は重要な法事です。
亡くなられてから49日に至るまでは非常に大事な期間であるという事です。
なぜ七日ごとに行うのか?
中有の世界においては七日目ごとに死後の世界の裁判官である閻魔がやってきて、その死者の生前の行為をたずね、それによって次の世界のどこに生まれるかを決定する、と言われている。だれしもがよりよい死後の世界に生まれたいと願うので、何とか生前の悪業を隠そうとするのだが、残念ながら、閻魔が持っている帳面にはすべての行為が余すところなく記録されているので、絶対に嘘をつくことができないことになっている。もしこんなところで嘘をついたとすると、当然地獄に落ちて舌を抜かれるのである
閻魔大王の尋問は1回ではなく七日ごとに行われるのですね。各七日目にはいつもより新鮮なお供え物に変える、お経をあげてみる、いつもより話かけてみるなど入念な供養を心がけたいものです。
生きている方々にとっても一週間を振り返る良い機会だとも思います。忙しい毎日で終わってしまっていないか、今週は人に優しくできたとか、善い行いを心がけたなど振り返るきっかけでもあると思います。振り返ることによって、実は毎日を無事に過ごせているのはご先祖様が見守ってくれているおかげと気づけるかもしれませんね。
いつから数えるのか
お亡くなりになられた日を1日目として数えます。月曜日に亡くなられたとすれば初七日は日曜日になります。毎週日曜日が大事な日となります。日にちで数えると数え間違いが置きやすいのでカレンダーを見ながら、亡くなられてから7回目の日曜日(今回の場合)が七七日忌と数えるとわかりやすいです。
まとめ
亡くなられた当日(命日)を1日目として数えます。
7日ごとに大事な日です。
納骨先がまだ決まっていない方は18時や19時から始まる法事はどうでしょうか?
土日に必ずしなければならないという決まりもありません。
49日目のぴったりの日にち(満中陰)に法事を行うことが可能となります。
故人を偲び、夕食も兼ねて食事を取られると自然な流れだと思います。
49日のことでお悩みの方はお問い合わせくださいませ